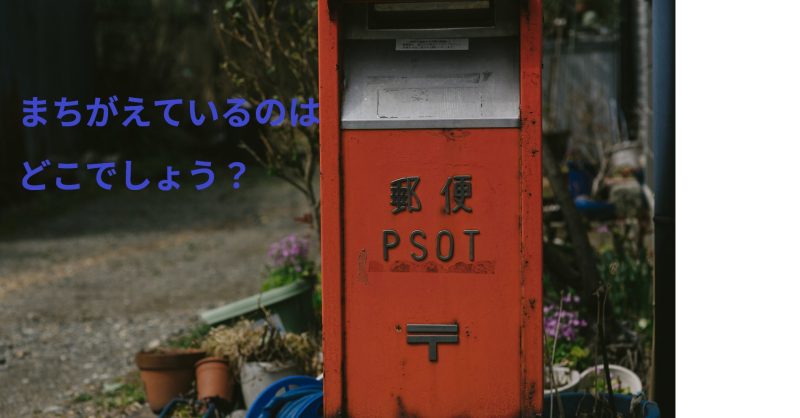
車線変更で横方向を目視確認している時に、前方の確認はどうするの?
そんな疑問を解決するのに中心視野と周辺視野の役割とトレーニング方法などの情報を下記にまとめてみました。
中心視野がカバーしている範囲は狭い

上記画像は視点を固定した所を中心に視野を分けたものです。
中心視野(うすいオレンジ)は書籍の音読などに使っています。
焦点を決めて狭い範囲に集中するほど、視野が1点に集まり微妙な変化や深いレベルでの分析などが出来ます。
中心視野は大雑把に物の動きを捉えるよりも、狭い範囲を集中的に正確に読み解くときに使っています。
長時間の集中は疲労が早くたまります。
こまめに休憩をとるように意識すると良いです。
周辺視野って何ができるの
車を運転中に、前を集中的に見ている時に、視野に写っている周りの景色などが見えている範囲をいいます。(中心視野とは別のものを見れる)
周辺視野は、中心視野よりも範囲が広くたくさんの情報を取り込めます。
授業中に友だちの顔を中心視野で見ながら、先生が投げてきたチョークを周辺視野で認識できれば、避けることだってできるはずです。
まだ運転に慣れていない人が直線道路でも左右にふらついたりするのは、直ぐ前を中心視野だけで、キョロキョロと視点が泳いでいるからでしょう。
慣れている人が長時間安定して運転できるのは、周辺視野を使って広く浅くたくさんの情報を取り込めているからです。
特に交差点の右左折や、車線変更は真っ直ぐ前の情報だけでは足りません。
右に頭を振って車線変更する時を考えると、中心視野を変更したい車線の死角に合わせて、周辺視野で前を見ています。
前方を周辺視野に捉えていても、突然のアクシデントには対応できない事だってありえます。
それを解決する方法としては、周辺視野に切り換える方向には事前に車間距離を空けておくことです。
私の場合は細かい洞察が必要な方向には中心視野がよく働いています。
周辺視野を使う状況は、周辺の状況が変化していたり、長時間の持続が必要な時に自然に切り換えができます。
ネット上にあった周辺視野のトレーニング用動画や画像を見つけたので良かったら試してみてください。

コメント