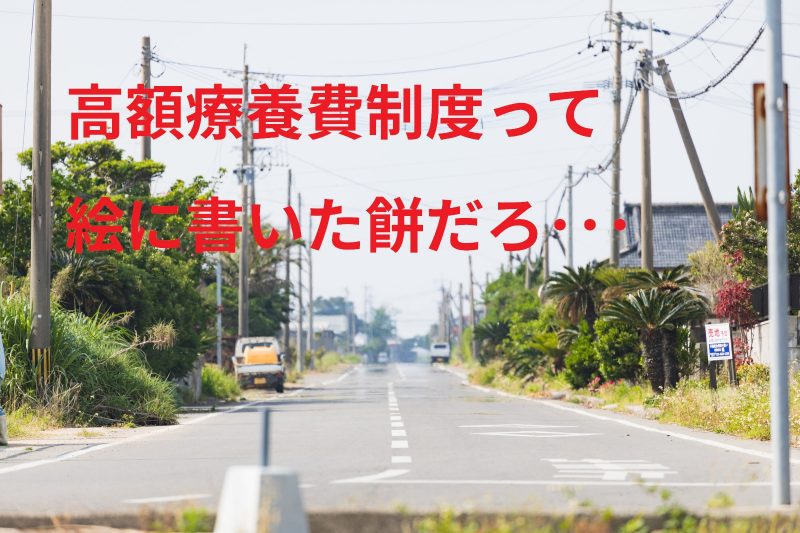
交通事故の怪我を健保で治療できるのは憶えたけど高額医療費制度ってなに?
長い間つらくて面倒で痛い治療を続けている、あなたを救済するための制度を発見したはずだった・・・
70歳未満の交通事故治療に絞って高額療養費制度の落とし穴をまとめました。
高額療養費制度の申請方法は2とおりある
- 事前に申請して自己負担限度額以上の支出を失くす。
- 事後に申請して自己負担限度額を越えた分を返金してもらう。
今回の状況は交通事故治療に絞っているので事前に予見することは不可能です。
1.事前申請は保険証を持って区役所の窓口に行くだけです。
2.事後申請は診察後に送られてくる支給申請書に必要事項を記入し領収書を添付して提出します。
なんだ簡単だな!っと思ったら、この申請書の記入のルールが面倒で各医療保険団体によって違いがあるみたです。
同じ病院でも受診した科ごとに分けるとか、治療(傷病名)ごとに分けて記入したりする団体があるので注意が必要です。
70歳を境に3つの年収ごとに一定の負担額を決定する
具体例として70歳未満で所得や年収によって3つの計算式に別れます。
| 所得区分 | ひと月あたりの自己負担限度額 |
| 年収約1160万円~ 健保:標報83万円以上 国保:年間所得901万円超 | 252600+ (医療費-842000))×1% 多数回該当140100 |
| 年収約770~約1160万円 健保:標報53万~79万円 国保:所年間所得600万~901万円 | 167400+ (医療費-558000)×1% 多数回該当93000 |
| 年収約370~約770万円 健保:標報28万~50万円 国保:所年間所得210万~600万円 | 80100+ (医療費-267000)×1% 多数回該当44400 |
| 年収約370万円~ 健保:標報26万円以下 国保:年間所得210万円以下 | 57600 多数回該当44400 |
| 住民税非課税者 | 35400 多数回該当24600 |
年収約370万~約770万円で実際にかかった医療費が40万円の具体例をあげます。
計算式(400000-267000)×1%+80100=81430
実費400000-自己負担限度額81430=318570
返金される金額は318570円です。
実際の医療費を約4分の3以上節約する効果があります。
世帯合算で自己負担限度額を上回れば適用される
受診先の医療機関が複数ある場合でも一定の条件で合算が認められています。
”同一の医療機関等における自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えな
いときでも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担(70歳未満の場合は2万1
千円以上であることが必要です。)を合算することができます。
この合算額が負担の上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
厚生労働省保健局より引用”
同じ世帯の家族でも、夫は健保組合に加入で嫁が国保のように医療保険の団体が違うものは合算できません。
同一月内の支払額が合計21000円以上(医療機関ごとの明細1枚ごとに)かかったものだけを合算する対象とします。
普通に生活している分で1ヶ月に21000円以上かかる保険治療を経験したことがないので、69歳で怪我をした人には地獄のような21000円縛りですね・・・
多数回該当でも自己負担限度額は引き下げられる
多数回該当とは
直近12ヶ月で3回以上高額療養費制度の払い戻しを受けたとき、4回目から自己負担限度額が更に低く設定される制度です。
ただし直近12ヶ月に違う団体(健保から国保への移動など)を合算して12ヶ月とすることは出来ません。
21000円の縛りを越えられない人が年間で3回も自己負担限度額を越えるのは、交通事故などの一時的な治療費くらいです。笑
70歳未満には、適用条件のハードルが高い制度です
一時的に受診回数が一気に増加しない限り21000円を越えるのは現実的ではありません。(自由診療はカウントされません)
その反面、高収入世帯と70歳以上には優しい制度です。
私も詳しく調べるまでは、メリットを感じていました。
70歳未満は21000円の壁を軽く越える人限定の制度でした。
高額療養費は適用外でも、健保での治療はメリットがあるので、必要な書類(第三者の行為による傷病届)を用意して試してみてください。

コメント